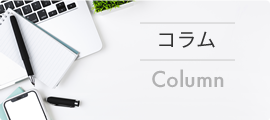テイクアウトの珈琲を選ぶときどんな選択をしていますか?
300円 と 400円の2択ならあまり差がでてこないのですが、300円、400円、500円の3択ならば、どうでしょうか?
そうです、400円を選ぶ人が多くなってきます。
松竹梅の法則と呼ばれるものですが、心理学では「極端性の回避」として認知されている行動です。
このように強制やルールではなく、より良い選択を自然に行えるようにするための工夫のことを「ナッジ(Nudge)」といいます。
2017年に行動経済学者のリチャード・セイラーとキャス・サンスティーンが提唱した概念です。
男子トイレの小便器には、的(まと)が書いてあることがあります。
便器の外に飛び散らないようにするための工夫ですが、まさにナッジを活用した事例です。
もしくは、
「いつも綺麗に利用して頂き有難うございます」と
トイレに貼ってあるメッセージもナッジを活用した例です。
保管場所に保管するモノの輪郭を描いて位置を指定し、誰が作業を行っても道具を正しい場所に戻せるようにする仕組み。
この整頓方法のことを「姿置き」とか「形跡整頓」と呼びますが、これもナッジの活用で、自然と定位置に戻す習慣がつく効果があります。
こんな感じで、ナッジという言葉は知らなくても、身近なところで多く活用されています。
何故 ナッジの活用なのか?
適切な行動を促すために、啓発活動や研修会の実施であったり、報奨金などのインセンティブ、社内規則の厳罰化をしたとしても思った効果が出ないことがあります。
知っているのに、実践しないとか
(例:電車等に列を作って並ばない大阪)
モノに釣られた時だけ行動する、
もしくは強制されないとやらない
などのように、自発的な行動を促す仕掛けがないと成果が出にくいです。
報奨金などで誘導する「外発的動機づけ」では、良い行動が長続きしないと言われています。
ナッジを活用する場合は、どのように行動するかではなく、人の行動や意思決定の特性に着目し、(内発的動機づけに着目し)行動選択の自由を保障した上で望ましい行動を後押しするので、効果が出やすいという訳です。
この時期に活用したいナッジ
さて、いつもより新しい人が会社組織に加わることが多いこの時期に、今の現状がどうであるか見つめ直して欲しいことがあります。
例えば、形骸化している「朝礼」
いつもワンパターンのやり方で、聞いている方は「朝礼の内容」を覚えているでしょうか?
数日してから、朝礼で指示した内容を振り返ってもらっても、「そんな話し、聞いてませんけど…」と真顔で返答されてないでしょうか?
もちろん、ワンパターンのやり方で参加しなくても影響の無い朝礼をしている方も悪いですが、自然と朝礼の内容を聞かないといけない「仕掛け」が必要です。
私が指導したものは朝礼の最後に「質問」を投げかけるやり方です。
〇〇さん、朝礼の中で伝達した
取引先の視察とはいつでしたか?
□□さん、提出するように指示された
書類とは何で、いつまででしたか?
このような質問を、誰に質問するか分からない緊張感の中で実施する方法です。
このようなナッジの活用で、朝礼で伝えたことが記憶に留まるようになりました。
また、組織がギスギスしていると困っていた会社に対して、コミュニケーションを促進するために、他人の「素晴らしい点」を発表してもらうことをしました。
ピアフィードバックと呼ばれる手法です。
他人の悪い部分にフォーカスするのではなく、良い部分、頑張っている部分に自然とフォーカスしてもらい、その意見をフィードバックすることで自分がどう見られているのか理解でき、(ギスギスするのではなく)お互いに認め合う組織になりました。
多少の時間はかかりますが、効果は期待できる仕掛けです。
(似たようなやり方で、ありがとうカードの方法も同じ仕掛けです)
これらの例はあくまで参考例ですが、ナッジの活用は「自発的な行動を促す」仕掛けです。
会社運営に無関心であったり、他人事のように構えている方にどうやったら望ましい行動を後押しすることができるのか。
ナッジの活用を通して、抱える問題にアプローチしてみましょう。
笑顔創造研究所は、みなさまの笑顔と地域経済を応援しています。